「みんなで考える地球の健康と私たちのwell-being」シンポジウムへの協力
(2024年11月30日)
2024年12月10日
2024年11月30日、ESG-IRECの星野俊也共同代表は、MA-T学会第2回年会の公開シンポジウム「みんなで考える地球の健康と私たちのwell-being」の企画に携わり、パネルディスカションの司会進行をしました。MA-Tとは、大阪大学発の革新的な酸化制御技術の総称で、水性ラジカルの活性度を制御することで、除菌・消臭から、感染症対策、高分子表面への機能付加、農薬・医薬品、抗がん剤への応用、また高難度の化学反応を常温常圧で可能とするなど、地球規模の課題解決に大きな期待がかけられています。(MA-Tについては、本ウェブサイト掲載の田畑彩生「MA-T System®―ミライへの希望と地球規模の課題解決を目指して」をご参照のこと。)
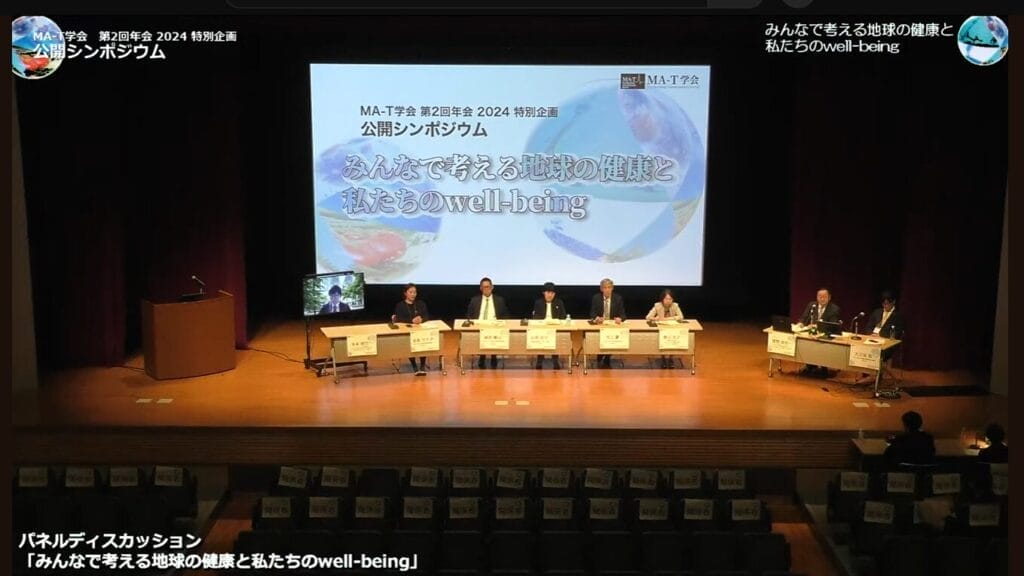
本シンポジウムの企画とパネルディスカションの司会進行を担当した星野俊也共同代表によるレポートは以下の通りです。
分子レベルでの革新的な酸化制御のメカニズムによって感染制御から医療・ライフサイエンス、食品衛生、農業・林業、新素材開発、さらには環境・エネルギー対策にまで多様な応用の可能性が広がるMA-T技術の社会実装を議論する学会で「地球の健康」と私たちの「ウェルビーイング」を議論するというのは突飛なようで、実は最も刺激的なのかもしれません。MA-T学会の公開イベントを担当する井上典子先生から今回の企画案を持ちかけられたとき、私はそう考えました。そこで、企画の趣旨として、次の一文をご提供し、そこからシンポジウムの骨格が固められていきました。
プラネタリーヘルス(Planetary Health)」という言葉があります。文字通り訳せば「惑星の健康」ですが、この惑星とは私たちの暮らす、かけがえのない地球です。したがって、これは「地球の健康」の意味になります。
みなさまが毎日の生活のなかで「地球の健康」にまで思いを巡らすことはほとんどないかと思いますが、本日は違います。
このシンポジウムでは、みなさまと一緒に、私たちのwell-beingが想像以上に地球の健康と密接にかかわっていること、しかも、私たち人間の経済社会活動や技術革新の急速な拡大や進展が地球環境と生態系と私たちのwell-beingとのバランスに重大な影響を及ぼしていることに目を向け、実感していただきます。その上で、私たちの想像力とイノベーションと実践行動を結集し、地球の健康と私たちのwell-beingが両立する、よりサステイナブルな未来の構築のための「次なるステップ」の具体的なアイデアや取組を議論します。
地球のキャパシティには限界がありますが、私たちの知的な活動にはバウンダリーもリミットもありません。文理の融合、産官学の共創、そして夢と現実の交錯を通じ、不可能と考えられていることや、逆に常識として受け入れられていることさえもひっくり返すような発想や視点も含め、あらゆる角度からの議論を期待しています。
当日は、長崎大学教授でFuture Earth国際事務局日本ハブ事務局長の春日文子先生に「プラネタリーヘルス実現に向けて−Sustainability Scienceと社会の連帯により、地球の未来のために今できること」というタイトルで基調講演をしていただいたのち、山本尚子先生(国際医療福祉大学大学院教授・前世界保健機関(WHO)事務局長補)、藤原康弘先生(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)理事長)、金森サヤ子先生(大阪大学全学教育推進機構教授)、寺本将行先生(ノースウェスタン大学医学部Health & Biomedical Informatics専攻博士課程学生・inochi未来プロジェクト理事)がそれぞれのお立場からのインプットがあり、それをMA-T技術のご専門のお立場から井上豪先生(大阪大学大学院薬学研究科教授)はパネリストとして、大久保敬先生(大阪大学先導的学際研究機構)は私とともに司会進行として、MA-Tシステムを応用し、いかに「プラネタリーヘルス」と私たちの「ウェルビーイング」をバランスさせていくかを考えていきました。
基調講演で春日先生が強調されたのは、この地球での出来事(気候変動、生物多様性の喪失、急激な都市化、貧困、大気汚染、水質汚濁、森林火災、大規模な洪水、永久凍土の融解、パンデミック、紛争と平和の危機、難民など)がすべて相互に関係があり、つながっていて、私たちの健康にも直結していること、そして地球の未来を決めるのは結局のところ私たちである、ということでした。また、春日先生は、ご紹介くださったFuture Earthが打ち出す「気候科学の10の新しいインサイト(洞察)」2024/2025年版では、メタン排出量を削減する方策やエネルギー転換に向けた取組、気温上昇への対応、極端現象が母体および生殖に関する健康に及ぼす脅威への対処、インフラのレジリエンスの強化など、MA-T技術が挑戦している課題ともつながっていることが見出されました。
パネルディスカションでは、まず、山本先生からは世界保健機関(WHO)や国連、経済協力開発機構(OECD)でのウェルビーイングの議論や取組が紹介され、日本における個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイングを結ぶ「地域包括ケアシステム」の役割、健康的な食のあり方などが論じられました。
藤原先生がご提起されたのは、私たちの健康やウェルビーイングに不可欠な医薬品の日本における承認遅れ(ドラッグ・ラグ)や未承認・未開発(ドラッグ・ロス)という極めて現実的な課題であり、今後の日本の創薬力の向上に向けた取組や国際展開の必要性を説かれました。
続いて登壇した金森先生からは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て、「身体的、精神的、社会的側面に焦点を当て、病気や疾患がないという心身の状態を指す」健康とともに、「心身の健康だけでなく、幸福感、充実感、生活の質といった主観的な体験も含む、より広い概念」として、単に生き延びるだけでなく、繁栄することも意味するウェルビーイングの重要性が広く認識されるようになったこと、そして、地球上のすべての命のウェルビーイングの向上を目指すためには現在の資源やシステムの維持を目指すにとどまる「サステイナブルな世界」を越えて、「リジェネラティブな未来」の創造、すなわち、自然や社会システムを「再生」し、以前よりも良い状態に戻すことを目指していくべきとの論点が提示されました。
若者のリーダーとして登壇をした寺本先生からは、その名も「inochi WAKAZO」プロジェクトといい、中高生も巻き込み、若者の力でいのちを守る社会を創るイノベーターやアントレプレナーの養成プログラムの実例や今後の展望が語られました。
こうした各パネリストからの問題提起や対話は分野を横断して共感やイマジネーションを促すものであり、井上先生や大久保先生が主導する課題解決型のMA-T技術の研究・開発・実践にとっては、まさに「MA-T」が意図する「マッチング・トランスフォーメーション」、つまり異なる物質が出会ったところで有機合成が発生し、大きな変革につながる、というプロセスとも重なるような大きなインプットになったと考えられ、お聞きいただいたMA-T学会の多くの皆さまにも有益な「気づき」を提供する機会になったものと期待しています。
私は、シンポジウムの冒頭の開会あいさつで一枚の写真をお見せしました。「地球の出(earth rise)」という題のついたカラー写真で、1968年のクリスマス・イブの日、アポロ8号の乗組員が月の周回軌道から撮影したもので、人類が初めて月の地平線上から地球が上るのを目撃した際の写真です。「かえがいのない地球」という言葉を聞くといつも私が思い浮かべるのがこの写真です。

大宇宙を背景に、太陽の光を浴びて青く輝く地球がとても美しく撮られています。ですが、その一方、地球が、寄る辺のない、かよわい存在のようにも見えます。地上にいれば広大と思われる地球も、実は宇宙のなかでは小惑星で、そのなかにいまや80億を超える人間がいて、資源の乱用や諍いをしている。MA-Tの科学と技術がそこで生じている課題の打開に大きな可能性を秘めていることは間違いありません。しかし、もう一つ、間違いのない現実は、私たちがこの地球の「いま」に責任を持つ住人として、未来の世代もずっとこの地球で豊かなウェルビーイングを実感できる暮らしができるように、一人ひとりが自らの発想や行動を転換していくことの大切さだといえましょう。










